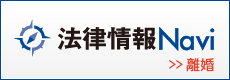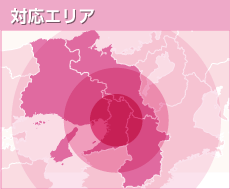1 成年に達した子の大学費用請求の可否
離婚にあたって、例えば、妻が子を引き取る場合、夫に対して子の将来の養育費を請求することができます。
何時までの養育費を請求できるについては、子が成人に達する月までとすることが一般的です。この点、大阪高裁昭和57年5月14日決定は、「父母が離婚している場合の未成年の子の養育費について、未成年の子を養育している親権者たる母は、自らが申立人となつて親権者でない父を相手方として・・・子の監護に関する処分として養育費の分担を請求しうるものというべきであるが、その子が成年に到達した場合には母の親権が終了するものである以上、右の子の監護に関する処分としての養育費の分担を請求しうるのは、子が成年に達するまでの分に限られるものであることはいうまでもない。」としています。
しかし、近時、子が大学に進学することも一般的であり、大学卒業までの費用を夫に請求できないかが問題となります。
2 子からの扶養料請求
上記大阪高裁決定は、母親の子が成人に達した以降の養育費請求を認めませんでしたが、子から父に対する扶養料の請求が認められた裁判例もあります。
例えば、東京高裁平成22年7月30日決定は、「一般に、成年に達した子は、その心身の状況に格別の問題がない限り、自助を旨として自活すべきものであり、また、成年に達した子に対する親の扶養義務は、生活扶助義務にとどまるものであって、生活扶助義務としてはもとより生活保持義務としても、親が成年に達した子が受ける大学教育のための費用を負担すべきであるとは直ちにはいいがたい。もっとも、現在、男女を問わず、4年制大学への進学率が相当に高まっており(略)、こうした現状の下においては、子が4年制大学に進学した上、勉学を優先し、その反面として学費や生活費が不足することを余儀なくされる場合に、学費や生活費の不足をどのように解消・軽減すベきかに関して、親子間で扶養義務の分担の割合、すなわち、扶養の程度又は方法を協議するに当たっては、上記のような不足が生じた経緯、不足する額、奨学金の種類、額及び受領方法、子のアルバイトによる収入の有無及び金額、子が大学教育を受けるについての子自身の意向及び親の意向、親の資力、さらに、本件のように親が離婚していた場合には親自身の再婚の有無、その家族の状況その他諸般の事情を考慮すべきであるが、なお協議が調わないとき又は上記親子間で協議することができないときには、子の需要、親の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを定めることとなる」とし、さいたま家裁越谷支平成22年3月19日審判を取り消して、父親に対し、子が大学を卒業すると見込まれる月まで一定額の支払いを命じました。
また、東京高裁平成12年12月5日決定も、「4年制大学に進学し、成人に達した子に対する親からの学費等の扶養の要否は、当該子の学業継続に関する諸般の事情を考慮した上で判断するべきであって、当該子が成人に達しかつ健康であることをもって直ちに当該子が要扶養状態にないと判断することは相当でない」として、成人に達した子からの扶養料請求を却下した横浜家裁平成12・9・27審判を取り消しています。
その他、大阪高裁平成2年8月7日決定、東京家裁昭和50年7月15日審判、福岡高裁昭和47年2月10日決定も、子の父親に対する扶養料請求において、大学卒業までの扶養料支払い義務を認めています。
3 妻の夫に対する養育費請求
しかし、子が成人するまでは妻から夫に対して養育費の請求を行い、子が成人に達した後は、子から父親に対して扶養料を請求しなければならないとすると手続が煩雑となり、妻から子が大学卒業するまでの養育費を請求できないかが問題となります。
この点、これを認めた裁判例がありますので、ご紹介しましょう。
東京地裁平成17年4月15日判決は、「養育費とは、子の監護に関する処分(民法第766条第2項)の一環として、監護親が非監護親に対して請求できるものであるところ、その前提として子が扶養必要状態にあること、即ち、未成熟であることが要件となるのであるから、一般的には成年に達した段階で未成熟子には当たらなくなるものというべきであり、親の養育費負担義務も消滅するのが原則と考えられる。しかし、その一方で、4年制大学への進学率が相当高い割合に達している現状において、子が義務教育に引き続いて高等学校、更には大学へと進学する場合、成年に達した後もなおその生活時間を優先的に勉学に充てることが必要となり、その結果、学費や生活費に不足を生じることはやむを得ないことというべきである。そして、本件においては、妻はもちろん、夫自らも、子供らが大学を卒業することを強く望んでいる旨明確に供述しているところであるが、・・・において認定したとおり、既に婚姻費用分担の審判を受け確定までしている以上、夫も、妻の収入については当然十分に承知しており、それを前提とした供述であることからすれば、この供述とは、夫において、子供らの大学進学に関する費用について自らが負担する旨の認識を示したものと判断することができる。また、もし、将来、子供らの中に大学に進学しない者が出たとしても、そのことが明らかになった段階で、夫において、家庭裁判所に養育費減額や期間伸縮等の申立てを行うことによって不合理な結論を避けることは十分に可能である。よって、本件においては、子供らが成年に達した後においても、4年制大学の卒業が予定される満22歳時までは、養育費支払義務が継続されるべき格別の事情が存在するものと認められ、夫が支払うべき養育費の終期は子供らの満22歳に達するまでと定めるのが相当である。」と判断しました。
また、東京地裁平成17年3月10日判決も、「妻は、子供らが満20歳に達した後の養育費の支払も一定条件の下に求めているところ、養育費は未成年者の子の扶養義務の一貫であることからすると、通常であれば成人に達する月までの支払が相当であるが、子供らが大学に入った場合については、その教育費がさらにかさみ、同人らの稼働もさほど期待できないこと、同人らが大学生になれば、その間の養育費を負担することについては、夫も了解していることを考えると、これを認めるのが相当であるが、子供らが、満20歳時に大学に在学していた場合であっても、その養育費の支払は在学中に限られるべき(退学等の場合は、自ら稼働等すべきである。)であるから、子供らが満20歳に達した日において、大学に在学する場合には同人らが満22歳の学年の年度末を限度として大学に在籍する月までとの限定のうえでこれを認めるのが相当であるといえる。そこで、夫は、平成○○年○月から、1人当たり月額8万円の割合の金員を支払うのが相当である。」としています。
ただし、上記裁判例は、夫も子が大学に進学することを望んでいる事案であり、全ての事案で上記と同様の結論になるとは限らないことに留意すべきです。
4 養育費の取り決めの重要性
離婚協議や離婚調停の際においても、将来、子が大学に進学する可能性があるのであれば、大学卒業時までの費用を支払うことを認めさせておけば、後日の紛争を避けることができます。
なお、東京地裁平成4年2月28日判決では、公正証書で定められた養育費につき終期の記載がなかった事案で、大学ないしこれと同程度の高等教育課程を修了するまでの趣旨だと解されていますが、このような紛争にならないためにも、養育費支払いの終期を明確に取り決めるべきでしょう。
(弁護士 井上元)