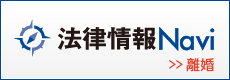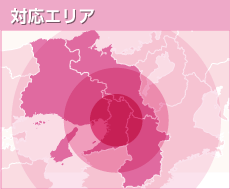離婚原因の一つとして「悪意の遺棄」(民法770条1項2号「配偶者から悪意で遺棄されたとき」が規定されています。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく民法752条の同居・協力・扶助義務を履行しないこととされています。裁判例で「悪意の遺棄」が問題とされることは少ないようですが、どのような場合がこれに当たるのか整理してみましょう。
(1)まず、「悪意の遺棄」について判断した最高裁判例として最高裁昭和39年9月17日判決(民集18巻7号1461頁)があります。同最判は、妻が夫の意思に反して妻の兄らを同居させ、その同居後において兄と親密の度を加えて、夫をないがしろにし、かつ兄などのため、ひそかに夫の財産より多額の支出をしたため、これらが根本的原因となつて夫は終に妻に対し同居を拒み、扶助義務をも履行せざるに至ったという事案で、「妻が夫との婚姻関係の破綻について主たる責を負うべきであり、夫よりの扶助を受けざるに至ったのも、妻自らが招いたものと認むべき以上、妻はもはや夫に対して扶助請求権を主張し得ざるに至ったものというべく、従つて、夫が妻を扶助しないことは、悪意の遺棄に該当しない」と判示しました。
以下は地裁の裁判例です。
(2)新潟地裁昭和36年4月24日判決(判例タイムズ118号107頁)
判決は、民法第770条第1項第2号の「遺棄」とは、正当の理由なくして同法第752条に定める夫婦としての同居および協力扶助義務を継続的に履行せず、夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否することを指称するところ、この 義務は守操義務とともに婚姻生活の基調をなすものであるため、結局婚姻共同生活の継続も廃絶する趣旨のことをいうものと解すべきであるとし、本件では、妻は格別の理由がないにもかかわらず無断家出して所在不明となり今日におよんでいるのであるから、妻はこの義務に違反し、遺棄という客観的要件を充足しているとしました。
しかし、配偶者が他方の配偶者を遺棄することによって離婚原因の形成されるためには、遺棄という事実のほかに、それが「悪意」をもってされたものであるという主観的(意思)要件が併せ存在することを必要とし、「悪意」とは、たんに遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているというよりも一段と強い意味をもち、社会的倫理的非難に値する要素を含むものであって、具体的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思(その意思は必らずしも明示的であることを要せず、当該配偶者の態度たとえば正当の理由なき同居の拒絶、長年にわたる音信不通などの事情から、明らかにその意思ありと推測されるなど黙示的であっても差し支えない。)をいうものと解するを相当とするとしました。そして、配偶者を遺棄した他方配偶者の所在が不明であることは悪意の要件ではなく、また他面そのような状態にあるという一事から直ちに悪意の存在を推定することは許されず、所在不明となるにいたった事由その他諸般の事情からみて、その配偶者に右にあげた婚姻共同生活の廃絶を企図し、もしくはこれを認容する意思の存在することが認定される場合に限って悪意ありとしうるにすぎないとしました。
(3)東京地裁昭和38年5月27日判決(判例時報349号54頁)
夫婦双方が、相手方から悪意で遺棄されたと主張した事案ですが、夫婦双方が勤務のため同居しなかったのであり共に悪意に遺棄にはあらないとしました。
(4)長野地裁飯山支部昭和40年11月15日判決(判例時報457号53頁)
夫が、妻と子を残して実家に戻り、漫然と放置した事案において、僅か2ヶ月で夫の悪意の遺棄を認めました。
(5)大阪地裁昭和43年6月27日判決(判例時報533号56頁)
夫が、余りに多い出張、外泊など妻ら家族を顧みない行動により、妻に対する夫としての同居協力扶助の義務を十分に尽さなかったことは「悪意の遺棄」にあたるとするにはやや足りないとしましたが、「婚姻を継続し難い重大事由」(5号)に当たるとして妻からの離婚請求を認めました。
(6)横浜地裁昭和50年9月11日判決(判例時報811号85頁)
妻は病気治療のため実家に帰り、その後夫の求めを無視して夫方に戻らなかったけれども、その間は約2ヶ月位であり、夫との共同生活を廃止する意思があったとは認められないから悪意で遺棄した場合に該当しないとしました。
(7)浦和地裁昭和60年11月29日判決(判例タイムズ56号70頁)
夫は、半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続け、その間妻に生活費を全く送金していないものであり、悪意の遺棄に該当するとしました。
(8)浦和地裁昭和60年11月29日判決(判例タイムズ615号96頁)
夫は、上京するに際し、妻に対し、出発予定も行先も告げず、爾後の生活方針について何ら相談することがなかったのであり、妻が3人の幼い子供を抱え、父親のいない生活を余儀なくされることを熟知しながら、敢えて夫婦、家族としての共同生活を放棄し、独断で上京に踏み切ったと認定し、悪意に遺棄にあたるとしました。
(弁護士 井上元)