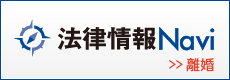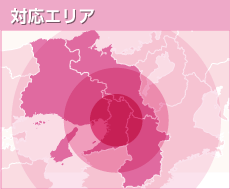1 養育費「子が大学を卒業する月まで」との条項
離婚調停において、未成年の子がいる場合、元夫が子の親権者となった元妻に対して、養育費を支払うことになります。通常、子が20歳になるまで支払う旨の内容が多いようですが、子が大学に進学する可能性が高い場合、「子が大学を卒業する月まで」との条項も見受けられるところです。
2 子が大学に進学しなかった場合
養育費支払いにつき、上記のような取り決めがなされても、子が大学に進学しなかった場合や4年制大学に進学しなかった場合(短期大学など)、いつまで養育費の支払いを受けることができるのでしょうか?
この点、東京地裁平成17年2月25日判決は次のように判示しています。
「なるほど、本件調停条項4項、5項には、上記のとおり、本件養育料等の支払義務の終期が明示されているけれども、大学の入学に特段の年齢制限等はなく(弁論の全趣旨)、また、扶養権利者である子が大学に進学するか否かは、その進学意欲、能力のほか、健康状態や進学のための資力等といった様々な諸要素により決定されるものといえるから、扶養の終期を「大学を卒業する月」までと定めたところで、一義的明確に扶養の終期が定められているとは解し得ない。もとより、家事審判において、扶養料の終期を大学卒業まで無制限と定めたとしても、一方において扶養権利者の要扶養状態が継続し、他方で扶養義務者において扶養可能な状態が続くのであれば、終期を定めずに扶養は継続されるべきものであるし、かかる事情が消滅すれば、当事者は、何時でも家庭裁判所に対する申立てにより扶養に関する審判の取り消しを求めることができるのであるから、上記のような定めが一概に違法であるということにはならないけれども、成年を過ぎた子と未成熟な未成年の子に対する扶養の義務は、その本質において異なるといえ、従って、その給付の内容、方法等も自ずと異ならざるを得ないというべきである。
さらに、本件調停条項4項、5項の合意をした際の調停当事者の意思についてみると、被告は、「昭和62年当時の原、被告間の共通認識として、両者とも大卒であったこともあり、大学を出ていなければ立派な社会人ではないという認識があったので、そのように書いた。」旨供述し(被告本人調書2頁)、原告も「2人の子どもが社会人になって自立するための学識、常識、人間関係を育むことを願っていた」旨供述しているのであって(原告本人調書2頁)、これらの供述からすれば、原、被告両名とも、敢えて具体的終期を定めず、春子らが大学を卒業するまで実質上無期限に被告が支払義務を負担するという趣旨で上記条項に係る合意をしたとまでは認めることができない。
このようにみれば、本件調停条項4項、5項は、春子らが成年に達した時点において、現に大学に在籍しているか、あるいは在籍していなかったとしても合理的な期間内に大学に進学することが相当程度の蓋然性をもって肯定できる特段の事情が存在する場合には、同人らが大学を卒業する月まで被告の本件養育料等の支払義務は延長され、そうでない限り、同人らが成年に達する日の前日をもって終了するとの趣旨で合意されたものと解するのが相当というべきである。」
そして、長女については、成年に達した時点において大学に進学していたとまでは認めるに足りず、その後、合理的な期間内に大学に進学することが相当程度の蓋然性をもって肯定できる特段の事情を認めるに足りる証拠はないとして、成年に達した日の前日をもって終了したと判断しました。
また、長男については、英国の音楽学校に進学していたところ、調停条項に定める「大学」の意義に関する原、被告の意思を合理的に解釈すれば、調停条項における「大学」とは学校教育法所定の大学を意味するものと解するのが相当であるとして、長男が成年に達した日の前日をもって終了したと判断しました。
3 調停条項はできるだけ具体的に記載
子の進路については、子が大きくなれば、子の意思で決めるべきものですので、両親の離婚の際、子が幼少である場合、いつまで養育費の支払いをうけるべきか不確定です。したがって、「子が大学そのた専門学校などの高等教育機関を卒業するまで」というような抽象的な取り決めをするしかありません。
これに対し、離婚の際に子が成長しており、ある程度、進路を具体的に想定することができる状況にあるなら、将来の紛争をなくすためにも、なるべく具体的に取り決めることが重要でしょう。
(弁護士 井上元)